В
гӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨпјҲEileen GrayпјүгҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹд»ЈиЎЁдҪңгҖҒгӮөгӮӨгғүгғҶгғјгғ–гғ«гҖҢE-1027гҖҚгҖӮ
еғ•гҒҜгӮ¬гғ©гӮ№зҙ жқҗгҒҢеҘҪгҒҚгҒ§иҮӘе®…гҒ®е»әжқҗгӮ„家具гҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҠж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
гғқгғ„гғігҒЁйғЁеұӢгҒ®дёӯгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҷгғғгғүгӮөгӮӨгғүгҒҢйҒ©еҲҮгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҒ“гҒ®гӮөгӮӨгғүгғҶгғјгғ–гғ«гҒҜеҚҳгҒӘгӮӢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘ家具гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж©ҹиғҪжҖ§гҒЁжҹ”и»ҹжҖ§гӮ’жҘөйҷҗгҒҫгҒ§иҝҪжұӮгҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғҶгғјгғ–гғ«гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨиҮӘиә«гҒҢе»әзҜүгҒЁе®¶е…·гӮ’дёҖдҪ“гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮеҪјеҘігҒҢиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгғўгғҖгғіе»әзҜүгҖҢE-1027гҖҚпјҲеҲҘеҗҚгҖҢгғӯгӮҜгғ–гғӘгғҘгғігғҢгҒ®еҲҘиҚҳгҖҚ1929е№ҙпјүгҒЁеҗҢгҒҳеҗҚгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒ®гғҶгғјгғ–гғ«гҒҜгҖҒеҖӢдәәгҒ®дҪңе“ҒгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгӮӮгӮігғ©гғңгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒЁиӘҝе’ҢгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒЁе®Ңе…ЁгҒ«йҖЈеӢ•гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҗҲгҒҶ家具гҒЁгҒ—гҒҰгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜиҝ‘д»ЈзҫҺиЎ“йӨЁгҒ®ж°ёд№…гӮігғ¬гӮҜгӮ·гғ§гғігҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж§ӢйҖ дёҠеҖӨж®өгҒҢе®үгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгғҹгғғгғүгӮ»гғігғҒгғҘгғӘгғјгҒ®ж„ӣеҘҪ家гҒҹгҒЎгҒ®е…Ҙй–ҖгӮўгӮӨгғҶгғ гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҢE-1027гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚеүҚиҮӘдҪ“гӮӮгҖҒеҪјеҘігҒЁгҒқгҒ®жҒӢдәәгҖҒгӮёгғЈгғігғ»гғҗгғүгғҙгӮЈгғғгғҒгҒ®гӮӨгғӢгӮ·гғЈгғ«гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгӮўгғ«гғ•гӮЎгғҷгғғгғҲгҒ®з•ӘеҸ·гҒ«гҒ—гҒҰжҡ—еҸ·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- Eileen пјқ E
- Jean пјқ 10 пјҲJ гҒҢгӮўгғ«гғ•гӮЎгғҷгғғгғҲ 10 з•Әзӣ®пјү
- Badovici пјқ 2 пјҲB гҒҢгӮўгғ«гғ•гӮЎгғҷгғғгғҲ 2 з•Әзӣ®пјү
- Gray пјқ 7 пјҲG гҒҢгӮўгғ«гғ•гӮЎгғҷгғғгғҲ 7 з•Әзӣ®пјү
В
гӮ¬гғ©гӮ№гҒ®гғҒгӮ§гӮ№гӮ»гғғгғҲгҒ®д»®зҪ®гҒҚе ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ
гӮ¬гғ©гӮ№гҒЁгӮҜгғӯгғјгғ гҒ®иіӘж„ҹгҒ«гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғ©гӮӨгғігҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҒҰж©ҹиғҪзҫҺгҒЁгҒӘгӮҢгҒ°гҖҒе»әзҜүгҒ®е·ЁеҢ гғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮЁгҒҢе”ёгӮӢгҒ®гӮӮзҙҚеҫ—гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒҷгҖӮ
йқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгҒЈгҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®е®¶гҒҗгӮүгҒ„гҒ—гҒӢдҪңе“ҒгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮ
гғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жүҚиғҪгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҘҪгҒҚеӢқжүӢдҪңгӮҢгӮӢиҮӘеҲҶгҒ®дҪңе“ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ®и§Јзӯ”гҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒеҪјеҘігҒҜиҮӘеҲҶгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒ—гҒӢдҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдёҚжҖқиӯ°гҖӮ
еҪјеҘігҒ«й–ўгҒ—гҒҰиӘһгӮүгӮҢгӮӢиЁҳйҢІгӮ„ж–ҮзҢ®гӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҖҒиіҮж–ҷгҒ•гҒҲгӮӮиҰӢгҒӨгҒ‘гҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖӮ
40жӯігӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҒӮгҒҹгӮҠгҒӢгӮү家具гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҜгҒҳгӮҒгҖҒе»әзҜүзү©гҒ®дёӯгҒ«зөЁжҜҜгӮ„з…§жҳҺгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгӮӢгҖҢгӮӨгғігғҶгғӘгӮўгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгӮ’дҪңгҒЈгҒҹе§ӢзҘ–гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәәгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеғ•гҒҜзҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиӢҘгҒӢгӮҠгҒ—жҷӮгҒ«ж—Ҙжң¬дәәе·ҘиҠёе®¶гғ»иҸ…еҺҹзІҫйҖ гҒ«еҫ“дәӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮж—Ҙжң¬гҒЁгҒқгӮ“гҒӘй–ўгӮҸгӮҠгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӘгӮ“гҒҰгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶз№ӢгҒҢгӮҠгҒЈгҒҰгҖҒгҒӘгӮ“гҒ гҒӢе¬үгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ
В
в– гӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨ - Wikipedia
гҒ•гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгҒ®гӮөгӮӨгғүгғҶгғјгғ–гғ«гҖҢE-1027гҖҚгҖӮ
гӮігғғгғ—гӮ’зҪ®гҒҸйҡӣгҒ«гӮ¬гғ©гӮ№йқўгҒ«гӮ«гғ„гғігӮ«гғ„гғійҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе°‘гҒ—ж°—гӮ’дҪҝгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒҜгҖҒгғҶгғјгғ–гғ«йқўгҒЁи¶іе ҙгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢз©әй–“гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹй…ҚзҪ®гҒҢгҒ§гҒҚгҖҒгғҷгғғгғүгӮ„гӮҪгғ•гӮЎгҒ«еј•гҒҚеҜ„гҒӣгҒҰдҪҝгҒҶдёҠгҒ«гғҗгғ©гғігӮ№гӮӮиүҜгҒ„гҒ®гҒ§дҪҝгҒ„еӢқжүӢгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
йҖ еҪўгӮӮеҘіжҖ§зҡ„гҒӘз№Ҡзҙ°гҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘзҫҺгҒ—гҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ
еҖӨж®өгӮӮ1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒйғЁеұӢгҒ«ж°—и»ҪгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯпјҒ
В
В
В
йҖҸжҳҺгҒӘгӮ¬гғ©гӮ№еӨ©жқҝгҒҜи»ҪгӮ„гҒӢгҒӘиҰ–иҰҡеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз©әй–“гҒ«ең§иҝ«ж„ҹгӮ’дёҺгҒҲгҒҡгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘгӮӨгғігғҶгғӘгӮўгҒ«гӮӮжә¶гҒ‘иҫјгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮжұҡгӮҢгҒҢжӢӯгҒҚеҸ–гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе®ҹз”ЁжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒиҖҗд№…жҖ§гҒ®гҒӮгӮӢеј·еҢ–гӮ¬гғ©гӮ№гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
В
В
зүҮжҢҒгҒЎж§ӢйҖ гҒ§и¶іе…ғгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒгӮҪгғ•гӮЎгӮ„гғҷгғғгғүгҒ®дёӢгҒ«е·®гҒ—иҫјгӮҒгӮӢгӮ«гғігғҒгғ¬гғҗгғјж§ӢйҖ гҖӮ
гӮҜгғӯгғ гғЎгғғгӮӯеЎ—иЈ…д»•дёҠгҒ’гҒ§йҢҶгҒігҒ«гҒҸгҒҸгҖҒиҖҗд№…жҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе®үдҫЎгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгғЎгғғгӮӯгҒҢеүҘгҒҢгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гҒӢгӮӮгҖӮ
гғ‘гӮӨгғ—гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜзҙ°гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁиҸҜеҘўгҒ§е®үе®ҡж„ҹгҒ«ж¬ гҒ‘гҖҒеӨӘгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®и»ҪгӮ„гҒӢгҒ•гҒҢжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢиүҜгҒҸйғЁеұӢгҒҢеәғгҒҸиҰӢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
В
иҰӢгҒҹзӣ®гҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж§ӢйҖ гғ»ж©ҹиғҪгғ»зҙ жқҗгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢзө¶еҰҷгҒӘгғҶгғјгғ–гғ«гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
В
В
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«жўұеҢ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘж„ҹгҒҳгҖӮ
гӮ¬гғ©гӮ№гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒӘгҒ®гҒӢжңЁз®ұгҒ®дёӯгҒ«еҸҺгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒ家гҒ«жҢҒгҒЎиҫјгӮ“гҒ жҷӮгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®жңЁз®ұгӮ’еүҚгҒ«йҖ”ж–№гҒ«гҒҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
В
В
В
з ҙгҒ„гҒҰй–ӢгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜжңЁжһ д»ҘеӨ–гҒ®ж®өгғңгғјгғ«йғЁеҲҶгҒ гҒ‘гҖӮ
жңЁжһ гҒҢй ‘дёҲгҒ«зө„гҒҫгӮҢгҖҒгҒ§гҒЈгҒӢгҒ„гғӣгғғгғҲгӮӯгӮ№гҒҝгҒҹгҒ„гҒӘгҒ®гҒ§еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгӮӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгҖҒ家еәӯгҒ«гҒӮгӮӢйҒ“е…·гҒҳгӮғеҲҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ®з„ЎзҗҶгҒҳгӮғгҒӯпјҹ
гғ»гғ»гғ»гҖӮ
гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гғ»гҖӮ
В
В
В
еј·еј•гҒ«гҒ„гҒЈгҒҹпҪһпҪһпјҒпјҒ
гҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгҒ“гҒ®жңҖеҫҢгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҹжңЁжһ гҒҜгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰжҚЁгҒҰгҒҹгӮүгҒ„гҒ„гӮ“гҒ гӮҚгҒҶпјҹ
В
В
В
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгғҶгғјгғ–гғ«гҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҜеҲҶи§ЈгҒ•гӮҢtгҒ“гӮ“гҒӘж„ҹгҒҳгҒ«з®ұгҒ®дёӯгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјҲеј•гҒЈејөгӮҠеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹпјүгҖӮ
зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜ 30 еҲҶгӮӮгҒӢгҒӢгӮүгҒҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҘіжҖ§гҒ§гӮӮе®үеҝғгҖӮ
В
В
ж—Ҙжң¬гҒЁж¬§зұігҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®йҒ•гҒ„
гӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгҒ®иЈҪе“ҒгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘһгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒеҪјеҘігҒ®гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҹҘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
В
жө·еӨ–гҒ§гҒҜгҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒҢгӮЁгғігӮёгғӢгӮўгҒЁеҜҫзӯүгҒӘз«Ӣе ҙгҒ§иЈҪе“Ғй–ӢзҷәгҒ«й–ўдёҺгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјпјқиҰӢгҒҹзӣ®гӮ’дҪңгӮӢдәәгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘҚиӯҳгҒҢж №еј·гҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгҖҢеӨ–иҰӢгӮ„иЈ…йЈҫгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ«еҒҸгҒЈгҒҰзҗҶи§ЈгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒжӯҙеҸІзҡ„гҒӘзөҢз·ҜгӮ„иЁҖи‘үгҒ®е°Һе…ҘжҷӮгҒ®еҪұйҹҝгҒҢй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҲdesignпјүгҖҚгҒҜгҖҒе…ғгҖ…гҒҜгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®гҖҢdesignareпјҲиЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҖҒиЁҲз”»гҒҷгӮӢпјүгҖҚгҒ«з”ұжқҘгҒ—гҖҒиӢұиӘһгҒ§гҒҜгҖҢиЁҲз”»гҖҚгҖҢиЁӯиЁҲгҖҚгҖҢж„ҸеӣігҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігӮ’еҗ«гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒ“гҒ®жҰӮеҝөгҒҢијёе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢйҒҺзЁӢгҒ§гҖҒж„Ҹе‘ігҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
В
жҳҺжІ»жҷӮд»ЈпјҲ19дё–зҙҖеҫҢеҚҠпҪһпјү
- иҘҝжҙӢгҒ®е·ҘжҘӯжҠҖиЎ“гӮ„зҫҺиЎ“гҒҢжөҒе…ҘгҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒҜ иЈ…йЈҫзҫҺиЎ“пјҲиЈ…йЈҫгӮ’ж–ҪгҒҷгҒ“гҒЁпјү гҒЁгҒ—гҒҰзҗҶи§ЈгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
- гҖҢеӣіжЎҲгҖҚгӮ„гҖҢж„ҸеҢ гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЁҖи‘үгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ
жҲҰеҫҢпјҲ1945е№ҙд»ҘйҷҚпјү
- е·ҘжҘӯиЈҪе“ҒгҒ®еӨ§йҮҸз”ҹз”ЈгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒиЈҪе“ҒгҒ®еӨ–иҰігӮ„гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
- гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒҜгҖҢгӮ°гғ©гғ•гӮЈгғғгӮҜгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҖҢгғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒӘгҒ©гҒ®иҰ–иҰҡзҡ„гҒӘеҲҶйҮҺгҒ§гҒ®дҪҝз”ЁгҒҢеәғгҒҢгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬гҒ®дәәгҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқиҰӢгҒҹзӣ®гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе®ҡзқҖгҖӮ
В
ж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұж–ҮеҢ–гҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҖҢж„ҸеҢ пјҲгҒ„гҒ—гӮҮгҒҶпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҜеҸӨгҒҸгҒӢгӮүеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜдё»гҒ«гҖҢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘиҰҒзҙ гҖҚгҒ«з„ҰзӮ№гҒҢеҪ“гҒҰгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- е·ҘиҠёгӮ„е»әзҜүпјҡж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұе·ҘиҠёгӮ„е»әзҜүгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеҪўгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҖҚгӮ„гҖҢиЈ…йЈҫгҖҚгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
- зқҖзү©ж–ҮеҢ–пјҡзқҖзү©гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜжҹ„гӮ„иүІгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҢдёӯеҝғгҒ§гҖҒгҖҢж©ҹиғҪзҡ„гҒӘиЁӯиЁҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҖҢиҰ–иҰҡзҡ„гҒӘзҫҺгҖҚгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиғҢжҷҜгҒӢгӮүгҖҒгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒЁиҒһгҒҸгҒЁгҖҢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢе…ҲиЎҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіж•ҷиӮІгҒ§гҒҜгҖҒзү№гҒ«жҲҰеҫҢгҒ®еӯҰж Ўж•ҷиӮІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқгӮўгғјгғҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҒҙйқўгҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- зҫҺиЎ“ж•ҷиӮІгҒ§гҒҜгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгҖҢиүІгӮ„еҪўгӮ’е·ҘеӨ«гҒ—гҒҰзҫҺгҒ—гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰж•ҷгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ
- дёҖж–№гҖҒ欧зұігҒ§гҒҜгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіжҖқиҖғпјҲDesign ThinkingпјүгҖҚгҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгҖҒе•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ®жүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’жҚүгҒҲгӮӢж•ҷиӮІгҒҢж №д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒ
- ж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒ§гҒҜй•·гӮүгҒҸгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғійғЁй–ҖгҖҚгҒҢгҖҢеӨ–иҰігӮ’жұәгӮҒгӮӢйғЁзҪІгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҖҒе·ҘеӯҰиЁӯиЁҲгҒЁгҒҜеҲҘгҒ®й ҳеҹҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
- иҘҝжҙӢгҒ§гҒҜгҖҢгӮӨгғігғҖгӮ№гғҲгғӘгӮўгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҲе·ҘжҘӯгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјүгҖҚгҒҢгҖҢиЈҪе“ҒгҒ®иЁӯиЁҲе…ЁдҪ“гҖҚгҒ«й–ўгӮҸгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҢе·ҘжҘӯгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқиЈҪе“ҒгҒ®иҰӢгҒҹзӣ®гҖҚгҒЁиӘӨи§ЈгҒ•гӮҢгҒҢгҒЎгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқиҰӢгҒҹзӣ®гӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘҚиӯҳгӮ’дёҖиҲ¬гҒ«еәғгӮҒгҒҹиҰҒеӣ гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
В
欧зұігҒ®гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„
В
еғ•гҒҜжө·еӨ–ж”ҜзӨҫгҒёгҒ®й•·жңҹеҮәејөгҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғізөұжӢ¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒҜзҫҺиЎ“гғ»иҠёиЎ“зі»гҒ®еӯҰж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжө·еӨ–гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒҜеҲҶйҮҺгҒ«гӮӮгӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢ зҗҶзі»гҒ®еӨ§еӯҰгӮ’еҚ’жҘӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒе·ҘеӯҰзҡ„гҒӘеӯҰе•ҸгӮ’еӯҰгҒ¶гӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гғ—гғӯгғҖгӮҜгғҲгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҲе·ҘжҘӯгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјүгӮ„ UX гғҮгӮ¶гӮӨгғі гҒӘгҒ©гҒ®еҲҶйҮҺгҒ§гҒҜгҖҒе·ҘеӯҰгӮ„ж•°еӯҰгҖҒзү©зҗҶеӯҰгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҗҶзі»гҒ®зҹҘиӯҳгҒҢеҝ…й ҲгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
欧зұігҒ§гҒҜгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
- гӮЁгғігӮёгғӢгӮўгғӘгғігӮ°гҒЁдёҖдҪ“еҢ–пјҡгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқиЁӯиЁҲгҖҚгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҶ…йғЁж§ӢйҖ гҒ®иЁӯиЁҲгӮ„ж©ҹиғҪжҖ§гӮ’еҗ«гӮҖгҖӮ
- UX/UIгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҡдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•гӮ„дҪ“йЁ“иЁӯиЁҲгӮӮгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ
- гғҮгӮ¶гӮӨгғіжҖқиҖғпјҡе•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ®жүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢеәғгҒҸиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
дёҖж–№гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҰӮеҝөгҒҢжөёйҖҸгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢйҒ…гӮҢгҖҒгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқгғ“гӮёгғҘгӮўгғ«гҖҚгҒЁиӘӨи§ЈгҒ•гӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
иҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіжҖқиҖғпјҲDesign ThinkingпјүгҖҚгӮ„гҖҢUX/UIгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒ®жҷ®еҸҠгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқиЁӯиЁҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҢе°‘гҒ—гҒҡгҒӨжөёйҖҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒй•·е№ҙгҒ®ж–ҮеҢ–зҡ„гҒӘиғҢжҷҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіиҰігҖҚгҒ®еӨүеҢ–гҒ«гҒҜжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӯҙеҸІзҡ„гҒӘзөҢз·ҜгӮ’зҹҘгӮӢгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁж¬§зұігҒ®гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒ®иӘҚиӯҳгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ
гғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒ®ж©ҹиғҪдё»зҫ©гҒЁгҖҒгӮўгғјгғ«гғ»гғҮгӮігҒ®з№Ҡзҙ°гҒӘзҫҺеӯҰ
гҖҢE-1027гҖҚгҒ®жңҖгӮӮзү№еҫҙзҡ„гҒӘиҰҒзҙ гҒҜгҖҒй«ҳгҒ•иӘҝж•ҙгҒҢеҸҜиғҪгҒӘж”Ҝжҹұж§ӢйҖ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢгӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ®иҝҪжұӮгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еҲ©дҫҝжҖ§гӮ’жңҖе„Әе…ҲгҒ—гҒҹиЁӯиЁҲжҖқжғігҒ®иЎЁгӮҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®ж©ҹиғҪгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮҪгғ•гӮЎгӮ„гғҷгғғгғүгӮөгӮӨгғүгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгӮ·гғҒгғҘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігҒ§жҙ»иәҚгҒҷгӮӢеҸҜеӨүжҖ§гӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮй«ҳгҒ•гӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйЈҹдәӢгӮ’гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғҲгғ¬гӮӨгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒдҪңжҘӯз”ЁгҒ®иЈңеҠ©гғҶгғјгғ–гғ«гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҒҫгҒҹжңҖе°ҸйҷҗгҒ®йғЁе“ҒгҒ§жңҖеӨ§йҷҗгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„ж§ӢйҖ зҫҺгҒ«гӮӮе”ёгӮүгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҶҶеҪўгҒ®гӮ¬гғ©гӮ№еӨ©жқҝгҒЁгӮ№гғҒгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгҒ„гҒҶйқһеёёгҒ«гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘиҰҒзҙ гҒ гҒ‘гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҚҳзҙ”гҒӘж§ӢжҲҗгҒҢеӢ•зҡ„гҒӘдҪҝгҒ„ж–№гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢж©ҹиғҪзҫҺгӮ’з”ҹгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гғҒгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гӮ’жӣІгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒи„ҡйғЁгҒҢзүҮжҢҒгҒЎж§ӢйҖ пјҲгӮ«гғігғҒгғ¬гғҗгғјпјүгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҷгғјгӮ№йғЁеҲҶгҒҢйӮӘйӯ”гҒ«гҒӘгӮүгҒҡгҖҒгӮҪгғ•гӮЎгӮ„гғҷгғғгғүгҒ®дёӢгҒ«ж»‘гӮҠиҫјгҒҫгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгғҹгғјгӮ№гғ»гғ•гӮЎгғігғ»гғҮгғ«гғ»гғӯгғјгӮЁгҒ®гҖҢгғҗгғ«гӮ»гғӯгғҠгғҒгӮ§гӮўгҖҚгӮ„гҖҒгғһгғ«гӮ»гғ«гғ»гғ–гғӯгӮӨгғӨгғјгҒ®гҖҢгғҜгӮ·гғӘгғјгғҒгӮ§гӮўгҖҚгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮ№гғҒгғјгғ«гғҒгғҘгғјгғ–гҒ®ж§ӢйҖ зҫҺгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒгӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгӮӮзҙ жқҗгҒ®жҢҒгҒӨеј·еәҰгҒЁгҒ—гҒӘгӮ„гҒӢгҒ•гӮ’жңҖеӨ§йҷҗжҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
В
гӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢж©ҹиғҪдё»зҫ©гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒгӮўгғјгғ«гғ»гғҮгӮігҒ®гӮЁгғ¬гӮ¬гғігӮ№гӮӮдҪөгҒӣжҢҒгҒӨзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒеӨ©жқҝгҒ®гӮҜгғӘгӮўгӮ¬гғ©гӮ№гҒҜз©әй–“гҒ«и»ҪгӮ„гҒӢгҒ•гӮ’з”ҹгҒҝгҖҒгӮ№гғҒгғјгғ«гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜзҙ°иә«гҒӘгҒҢгӮүгӮӮиҰ–иҰҡзҡ„гҒӘгғӘгӮәгғ гӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘиҰҒзҙ гӮ’еүҠгҒҺиҗҪгҒЁгҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢгҒҹгӮ·гғ«гӮЁгғғгғҲгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгҒҢжҢҒгҒӨж§ӢйҖ гҒЁзҫҺгҒ—гҒ•гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№ж„ҹиҰҡгҒ®иіңзү©гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
В
еҪјеҘігҒҜгҖҢE-1027гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе»әзҜүгӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒгҒқгҒ®з©әй–“гҒ®дёӯгҒ§гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дәәгҒҢеӢ•гҒҚгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®¶е…·гҒҢж©ҹиғҪгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’еҫ№еә•зҡ„гҒ«иҖғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгғүгғҶгғјгғ–гғ«гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹ家具гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе»әзҜүгҒЁиӘҝе’ҢгҒҷгӮӢдёҖйғЁгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
В
гҒ“гҒ®гғҶгғјгғ–гғ«гҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮж©ҹиғҪзҡ„гҒ§зҫҺгҒ—гҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®иұЎеҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгҖҢиӘҝж•ҙеҸҜиғҪгҖҚгҖҢгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢйҖ гҖҚгҖҢз”ЁйҖ”гҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®гғҹгғӢгғһгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјдёӯеҝғиЁӯиЁҲпјҲUCDпјҡUser-Centered DesignпјүгҒ®е…Ҳй§ҶгҒ‘гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘з”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§еҪ№гҒ«з«ӢгҒӨгҒӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢвҖ”вҖ”гҒ“гҒ®гҖҢE-1027гҖҚгҒҜгҖҒгҒқгҒ®е“ІеӯҰгӮ’дҪ“зҸҫгҒ—гҒҹеҗҚдҪңгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
В
В
дёҠгҒ®й …зӣ®гҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғіпјқж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгӮ„ж©ҹиғҪиЁӯиЁҲгҒЁжӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҖҢE-1027гҖҚгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒ®зҗҶжғіеҪўгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гғҶгғјгғ–гғ«гҒҜгҖҒж§ӢйҖ гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдҪҝгҒ„ж–№гҒ«еҝңгҒҳгҒҰеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгӮӨгғігӮҝгғ©гӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒӘеӯҳеңЁгҒ§гҒҷгҖӮ
В
гӮўгӮӨгғӘгғјгғігғ»гӮ°гғ¬гӮӨгҒҜгҖҒ1920е№ҙд»ЈгҒЁгҒ„гҒҶжҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’еӣәе®ҡзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжөҒеӢ•зҡ„гҒ§гҖҒз’°еўғгӮ„дәәй–“гҒ®иЎҢеӢ•гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӨүеҢ–гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®гғ•гғ¬гӮӯгӮ·гғ–гғ«гҒӘгӮӨгғігғҶгғӘгӮўгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гӮӮйҖҡгҒҳгӮӢгҖҒйқһеёёгҒ«е…ҲйҖІзҡ„гҒӘиҖғгҒҲж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
В
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢE-1027гҖҚгҒҜгҒҹгҒ гҒ®гғўгғҖгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®еҗҚдҪңгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®жң¬иіӘгӮ’е•ҸгҒ„зӣҙгҒҷйқ©ж–°зҡ„гҒӘдҪңе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҰӢгҒҹзӣ®гҒ»гҒ©иӨҮйӣ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„
гӮ¬гғ©гӮ№еӨ©жқҝгҒҜгӮөгғғгҒЁжӢӯгҒҸгҒ гҒ‘гҒ§жұҡгӮҢгҒҢжӢӯгҒҚеҸ–гӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгӮ№гғҒгғјгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гӮӮйҢҶгҒігҒ«гҒҸгҒ„д»•дёҠгҒ’гҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжүӢе…ҘгӮҢгҒҢз°ЎеҚҳгҒ§й•·гҒҸзҫҺгҒ—гҒ•гӮ’дҝқгҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢйҖ гҒ§гғӣгӮігғӘгҒҢжәңгҒҫгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒжүӢе…ҘгӮҢгҒҢз°ЎеҚҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гғӘгӮ№гғҡгӮҜгғҲгӮ’еҝҳгӮҢгҒҡгҒ«
жұәгҒ—гҒҰе®үдҫЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгӮ’и¶…гҒҲгҒҰж„ӣгҒ•гӮҢгӮӢж©ҹиғҪзҫҺгҒЁиҖҗд№…жҖ§гӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒдёҖз”ҹгғўгғҺгҒ®дҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
-
иіје…ҘйҮ‘йЎҚ
17,500еҶҶ
-
иіје…Ҙж—Ҙ
2015е№ҙ05жңҲ23ж—Ҙ
-
иіје…Ҙе ҙжүҖ
гӮӨгғігғҶгғӘгӮўгӮ·гғ§гғғгғ—








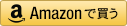
ZIGSOWгҒ«гғӯгӮ°гӮӨгғігҒҷгӮӢгҒЁгӮігғЎгғігғҲгӮ„гҒ“гҒ®гӮўгӮӨгғҶгғ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғҰгғјгӮ¶гғје…Ёе“ЎгҒ«иіӘе•ҸгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ