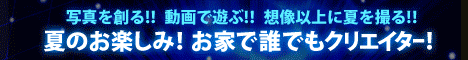- top
- ガイド撮影で長時間露光にチャレンジしよう
- 星雲・星団の画像処理
- ハイエンド・アマチュアの世界
- 天体写真のいろいろな楽しみ方
ハイエンド・アマチュアの世界
現在販売されているデジタルカメラは、天体写真向けには作られてはいない。そこでアマチュア天体写真の世界では、デジタルカメラを天体用に改造したり、天体写真用に開発された冷却CCDカメラを使ったりしている人も多い。ハイ・アマチュアの世界をちょっと覗いてみよう。
デジタルカメラの改造モデル
人間の肉眼で感じることができる波長の光を“可視光線”という。可視光線の中でも緑には感度が高く、赤や青は感度が低いという特性がある。天体写真でよく見かける赤い散光星雲は、赤外に近い波長の光を出しており、肉眼ではその波長の感度がほとんどない。一方で、デジタルカメラに使われている撮像センサーは十分な感度を持っているが、人間の見た目に合わせるために、撮像センサーの前にフィルターを取り付け、一部の波長の光をわざとカットしている。その結果、赤い散光星雲の波長もカットされてしまうのだ。
これでは散光星雲の写真撮影を楽しめないので、アマチュア天体写真の世界ではデジタルカメラのフィルターを取り外したり、天体写真に適切なフィルターに換装した“改造デジタルカメラ”が一般的に使われている。
さらなる改造を施したカメラもある。撮像センサーのノイズは温度が高いほど強くなることが分かっているので、デジタルカメラのボディを大幅に改造し、センサーにペルチェ素子を貼り付けて冷やすのだ。これによりノイズを劇的に減らし、クオリティの高い作品を撮れるようになる。
これらの改造は個人では難しいが、一部の天文ショップがサポート付きで改造サービスを行っている。

改造をしていないノーマルのカメラだと、赤い散光星雲(水素輝線の波長656nm)のガスがほとんど写らない。撮像センサーには感度はあるものの、センサーとレンズの間に組み込まれている赤外カットフィルターにより大幅に減光されてしまっているからだ。その波長を透過するフィルターに交換したものが“天体要改造デジカメ”ということになる。

ノイズを減らすための最も効果的な手法は冷やすことだ。なんと、市販のデジタルカメラに冷却改造を加えたモデルも一部の天文ショップで販売されている。撮像センサーにヒートパイプならぬヒートプレートを接着させ、2段ペルチェ素子とヒートシンク、冷却ファンで構成された外部冷却器で放熱させるというもの。もちろんプロの職人によるカスタム品であり、結露対策まで万全を期している。これにより撮像センサーの温度は、気温より20〜30℃も低くなるため、ノイズが劇的に減少する。
天体写真専用の冷却CCDカメラ
上記のように、一般撮影用のデジタルカメラを天体写真用に改造するのではなく、元から天体写真用に開発されているカメラもある。これらのカメラには、もれなく冷却機構が内蔵されているため、“天体用冷却CCDカメラ”と呼ばれている。デジタルカメラのようにカメラ単体で撮影はできず、シャッターの制御や画像の保存のためにパソコン(と制御用のソフトウェア)が必須となる。一般撮影用の機能は何一つといっていいほど付いていない。波長をカットするフィルターもユーザー側で装着しない限り付いていないので、撮像センサーの性能の限り、すべてが写る。
とはいえ、撮影そのものはデジタルカメラで行う作業と大して変わらない。デジタルカメラをPCとUSBで接続して、ソフトウェアでシャッター制御するテザー撮影はほとんどの機種に用意されている。冷却CCDカメラの撮影方法は、テザー撮影そのものだ。
デジタルカメラと最も違う点は、モノクロの撮像センサーが広く使われているということだろう。なぜ今さらモノクロと思うかもしれないが、この方がカラーの撮像センサーより画質面で有利だからだ。
もちろん、そのまま撮影したら単なるモノクロ画像にしかならないが、撮像センサーの前に、赤(R)、緑(G)、青(B)のフィルターを使って、色毎に分けて撮影し、それらの画像をソフトウェアで合成してカラー画像を作り出している。この手法を“RGB合成”という。
RGB合成といった手法が採れるのは、天体写真はごく一部の例外を除くと短時間でその姿を変えない、時間変化ゼロな対象だからだ。よって色別に撮影して合成してもズレて重なったりすることはない。私たちがよく見るハッブル宇宙望遠鏡やすばる望遠鏡による天体写真もモノクロCCD撮影+RGB合成などで得られた画像だ。
対して撮影対象が刻一刻と変化してく一般写真では、“RGB一発撮り”が必須なので、デジタルカメラにはカラーセンサーが搭載されている。カラーセンサーは、赤と緑と青のピクセルが交互に並んでいるため、例えば1000万画素の撮像センサーでは、赤と青は250万画素ずつ、緑は500万画素と役割が決まっている(緑が多い理由は省略)。各色で1000万画素の解像力があるわけではないのだ。
モノクロCCD+RGB合成ならば各色1000万画素をフルに使えるため、解像力はすべて100%だし、カラーセンサー特有の“偽色”も原理的に発生しない。強いていえば撮影に3倍の時間がかかることがデメリットだ。

天体写真撮影専用の冷却CCDカメラ。海外製が多いが、日本でも数社が製作している。量産数が少ないため、デジタルカメラより高価なものばかりだが、その写りはデジタルカメラとは別次元。天体写真ファンの憧れのデバイスなのだ。

CCDカメラの前面カバーを開けたところ。モノクロの撮像センサーの手前に、カラーフィルターをつけて色別に撮影する。フィルターは円弧状に配置され、PCからの指令により自動で回転するようになっている。波長を精密に分離するために干渉系のフィルター膜を使っており、外見からは色がわかりにくいが、枠番号順に赤、緑、青、透明の4枚のフィルターが装着されている。

宇宙に散らばる淡いガスの濃淡まで写し撮ることができるのは冷却CCDカメラならでは。作例は、さそり座の一等星アンタレス(左下の黄色いガスに隠されている星)とそのまわりの散光星雲だ。カラフルな色彩は、ガスの成分や光源となる恒星の色の違いによるもので、疑似着色などではない。
- ・画像の編集がし易く、フルHD(1920x1080)の高解像度液晶採用17インチ大画面ノート
- ・ノートタイプでありながら16GBメモリを搭載。高解像度画像ファイルを複数枚開いたり、多重フィルタを一度にかけてもスムーズに動作します。
- ・動画ファイルの保存には、ハードディスクの交換が容易な外付けUSB3.0HDDクレイドルを用意
- ・世界最速のノート用CUDAグラフィックス GeForce GTX 580M搭載
高負荷時にパフォーマンスを引き上げる「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0」や、1つのコアで2つのスレッドを同時に実行する「インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー」を搭載しており、写真や映像の編集などのマルチメディア処理や、ゲームも快適に行えます。